|  耀き-第三の手紙 耀き-第三の手紙
そうして、薄暮の光が灯される。水、瞳、窓へと何百という投影が灯される。ご存知のように、自分の臓器、あるいは、体の白熱でその界隈を照らす者もいます。南の庭のヒカリコメツキ、藁についたツチボタル、水辺に棲んでいて怪物のような額に照明を持つ生き物たち。その中でも非情なものは、ハラタケで覆われた腐敗木の果てない小暗さ・・・・・・。
ここタイナロンにも、毎晩気になる者がいます。それらは、細い光のベールを分泌し、ときどき興奮しながら煌々と、そして爛々ときらめいています。道で私のそばを足早に―すいっと、見るからにダンスステップを踏んで―通り過ぎてゆく姿にうっとりと見惚れています。夕暮れ時になって家に姿を現しますが、長い昼の間は何をしているのか、見当もつきません。おそらく眠っているのでしょう。
今までに、一人で行動している姿を見たことがなく、市場や広場で何らかの決まった踊りをしながら、群れをなしたり自由にフォーメーションを組んだりして行動しています。しかし、雨や風の強い日には、閃光人はロウソクのように消え、屋根の下へと姿をくらますのです。逆境や厳しい気候、圧しかかる仕事や予期せぬ激変は彼らに似合いません。姿を見かけると、いつもこう思うのです。どこかでパーティーをやっていて、お楽しみが待ち構えているな、と。本当に快活で底抜けに明るく見え、バラのように赤く、もしくは黄なりを帯びた白熱は、どのパーティー会場をも飾り立てるようです。
町の中心に階段があるのですが、その近辺にタイナロン人が夜ごと交際の場を求めにやって来たり、ただ顔を見るために集まってきます。押しも押されず派手な者、個性があまりある者、抜群に上品な着こなしの者、一番のお金持ち、そして一番の貧乏人が、そこで、その近辺で、数百年も経った階段で落ち合うのです。ヒカリコメツキもまた―小さな発火人にまさに似つかわしい名前だと思いませんか?―帳が降りるとすぐに現れます。ただし、天候が凪いで暖かかったらの話ですが。
じっと見ていると切ない気持ちになりますが、接触しようとしたことはありません。この町の公用語を話しているとは思えないし、だいたい話すのかどうかさえも知らないのです。綿毛のように愛らしく、誰もが過ごしたことのない青春時代のように泡沫なのです。
最近何度も、その耀きを嬉々として見んばかりにその階段付近へと足を運んでいます。私に気づかぬまま、私のそばを、乞食人のそばを、青ベルトを付けて着飾った騎士のそばを小躍りしながら(!)素通りすると、その周りには希望が微かに揺らめき、春の息吹がさらりと漂うのです。まるで、何も失われていないかのように。
しかしながら、これは言っておかなければなりません。昨日の朝、ある脇道に向かう途中、市場に立ち寄ったときでした。溝の中で埃を被った雑巾を目にしました。その向こうでいくつかの哀れな背中が丸まっていました。そのそばを足を止めることなく通り過ぎましたが、角まで来たところで振り返ったのです。地面から持ち上げられ、運び去られる様子を目の当たりにしました。そのときやっと分かったのです。私は、ある発火人を、今回は一人ぼっちの発火人を見ていただけだと。それは、もはや青白くさえも発光していませんでした。本当に小さくて、暗い塊でした。喜悦のきらめき、人生の触発は消えてしまったのです。どこにだって、いつだって、その消滅を証明できてしまうのです。治る見込みのない、そんな辛い苦しみが視力を落とし、私からも人生の小さな日々を蝕んでゆきます。
今夜、町ではヒカリコメツキが大群となって再び動き出します。まるで春の鳥の群れのように、いつになく嬉しそうに、そしていつになく耀いて。
|
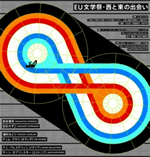 EU議長国オランダが中心となって企画した文化イベント、EU文学祭・西と東の出会い(West
goes east and the ywain will meet)が2004/11/7(日)に東京の六本木で行われました。EU加盟国を代表して、ティム・クラベ(オランダ)、アルド・ノーべ(イタリア)、ジョン・マクガハン(アイルランド)、グレゴール・ヘンス(ドイツ)、レーナ・クルーン(フィンランド)、ヨナス・メカス(リトアニア)、ヤーン・カプリンスキー(エストニア)といった作家達が参加しました。
EU議長国オランダが中心となって企画した文化イベント、EU文学祭・西と東の出会い(West
goes east and the ywain will meet)が2004/11/7(日)に東京の六本木で行われました。EU加盟国を代表して、ティム・クラベ(オランダ)、アルド・ノーべ(イタリア)、ジョン・マクガハン(アイルランド)、グレゴール・ヘンス(ドイツ)、レーナ・クルーン(フィンランド)、ヨナス・メカス(リトアニア)、ヤーン・カプリンスキー(エストニア)といった作家達が参加しました。
 耀き-第三の手紙
耀き-第三の手紙